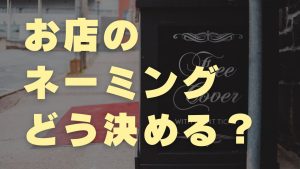今、飲食店の現場で注目されているのが業務用うどん製麺機です。
材料費の削減はもちろん、熟練の職人がいなくても安定したコシと食感を再現できるのが大きな魅力。さらにオリジナル麺の開発やアレルギー対応麺まで自由自在。
SNSでも自家製うどんの発信がトレンドになり、集客力アップにも直結しています。
この記事では、2025年最新のおすすめうどん製麺機ランキングTOP10と、導入時に必ず押さえたい選び方のポイントを徹底解説。店舗の規模やニーズに合った一台がきっと見つかります。
業務用うどん機械とは?導入のメリット
業務用うどん機械とは、「ミキサー」「圧延機(ロール)」「カッター(切り出し)」「ゆで槽」といった製麺工程に必要な機能を一体型またはユニット型で構成した装置のことを指します。
- 麺のコスト削減と安定供給
- 手打ち風食感の再現で味のクオリティUP
- 人件費削減・作業の均質化
- オリジナル麺で差別化可能(全粒粉、ゆで麺設定など)
導入を検討する際は、これらの構造を理解しておくことで、その効果やメリットをより具体的にイメージしやすくなるでしょう。
麺のコスト削減と安定供給
まず最大のメリットは、麺のコスト削減と安定供給の実現です。粉と水の配合を機械が自動で計量してくれるため、仕込みにおける材料ロスがほぼゼロになります。
たとえば、ある店舗ではかつて手練りで仕込んでいた頃は歩留まりが90%程度でしたが、うどん機械導入後には97%にまで向上。10kgあたり約70円のコストダウンとなり、月に1,000食提供する店舗では、年間で約25万円の原価削減につながります。
手打ち風食感の再現で味のクオリティUP
次に注目すべきは、味のクオリティ向上。最新機種では、熟成時間や圧延時の圧力を数値で細かく調整できるため、職人のような「コシ」や食感を再現することが可能です。
手打ちうどん特有の「エアポケット」と呼ばれる気泡入りの食感を再現できる、特殊な凹凸ロールを備えたモデルもあります。
人件費削減・作業の均質化
人件費の削減と作業の均質化も大きな利点です。うどん機械は、1人でも仕込みから製麺、茹で作業まで一連の工程を完結できる設計になっており、属人化を防ぎながら効率的な運営が可能になります。
たとえば、週6日勤務していた熟練職人の代わりにパート勤務のメンバーでも仕込みが出来るようになり、人件費を約25%削減できたケースもあります。
オリジナル麺で差別化可能(全粒粉、ゆで麺設定など)
オリジナル麺による差別化にも対応しています。全粒粉麺や平打ち麺、細うどんなど、ロールの厚みや水回しの速度を変えるだけで、多様なバリエーションの麺を自在に製造することが可能です。
例えば、米粉をブレンドしたアレルギー対応麺を開発し、客単価が1食あたり+120円になるなど、商品価値を高めることにもつながった例もあります。
季節限定の茹で麺を新たに展開して、SNSを活用した集客に繋げたりも出来るのが魅力ですね。
業務用うどん製麺機を導入する際にチェックすべきポイント
業務用うどん製麺機を導入する際にチェックすべきポイントを紹介します。
- サイズと設置スペースの確認
- 生産量と店舗の提供数に合っているか
- 操作性とメンテナンスのしやすさ
- アフターサービスと修理対応
① サイズと設置スペースの確認
小規模店舗の場合、厨房のスペースは限られていることが多いです。
業務用製麺機でも、コンパクト設計のものや、縦型・卓上型の製品もあります。購入前に必ず設置可能な寸法(幅・奥行・高さ)と搬入経路を確認しましょう。
② 生産量と店舗の提供数に合っているか
小規模店なら1日のうどん提供数が100~200食程度かもしれません。製麺機のスペック(1時間あたりの生産量)が、「作りすぎない」「不足しない」バランスで選ぶのが重要です。
手打ち感のある仕上がりを重視するなら、半自動型も検討の価値あります。
③ 操作性とメンテナンスのしやすさ
小規模店では多くの場合、オーナー自身が操作することが多いです。
誰でも簡単に使える操作パネルや、部品の取り外し・洗浄が簡単かが大事。メンテナンス性が悪いと、故障や衛生面のトラブルの元になってしまうでしょう。
④ アフターサービスと修理対応
機械が止まると即営業に支障が出るため、サポート体制はとても重要です。地元に拠点があるメーカーや、迅速な修理・部品供給が可能な会社を選ぶのが安心。
また、初期の使い方指導やレシピサポートがあるメーカーもおすすめです。
業務用うどん製麺機ランキングTOP10(2025年版)
以下にて、業務用うどん製麺機ランキングTOP10(2025年版)を紹介します。
1位:大和製作所「スーパー真打」

参照:https://www.yamatomfg.com/noodle-machines/udon-noodle-making-machine/super-shinuchi/
「スーパー真打」は、業務用製麺機の中でも非常に高い評価を受けています。幅1,335mmと比較的コンパクトで、厨房スペースが限られた個人経営の店舗にも無理なく導入可能です。
1時間あたり250〜300食という高い生産能力を持ちながら、操作もシンプル。内部は継ぎ目のない設計で、清掃やメンテナンスが非常に楽です。
全国サポート体制も完備されており、故障時の対応も安心。サイズ、生産性、操作性、アフターケアの全てが高水準で、総合力の高さが1位の理由です。
2位:不二精機「小型ロール製麺機RMT」

参照:https://www.fuji-seiki.co.jp/simulation/rmt
不二精機の「RMT」は、W1,263×D640×H1,202mmと非常に省スペース設計。厨房が狭い個人店にもぴったりです。生産量は100~150食/時と、個人店舗にちょうどよい規模感。
特筆すべきは、タッチパネル式の製麺ナビゲーション搭載で、初心者でも簡単に製麺が可能な点。さらに、うどんだけでなく低加水のラーメンやそばにも対応可能で、多店舗展開やメニューの多様化にも柔軟に対応できます。
サポート体制の詳細が不透明なため2位ですが、コストパフォーマンスと機能性は抜群です。
3位:スズキ麺工「めん屋の楽麺くんジュニア」

参照:https://turuturu.co.jp/seimen-kikai/rakumenkun-jr-2/
スズキ麺工の「楽麺くんジュニア」は、とにかくスリムでコンパクト。厨房のわずかなスペースにも設置でき、個人経営やテイクアウト専門の小規模店に最適です。一人でも十分に製麺ができるシンプル設計で、操作性が抜群。
手間をかけずに本格的なうどんが作れる点が魅力です。生産量は公表されていませんが、1日100食前後の小規模店舗には十分な性能といえます。
アフターサービスや耐久性の面でやや不透明な点があるため3位ですが、省スペース性と簡単操作は大きな強みです。
4位:さぬき麺機「小型手打ち式製麺機」

参照:https://www.menki.co.jp/teuchi001
さぬき麺機の「小型手打ち式製麺機」は、名前の通り本格的な手打ちうどんの風味と食感を再現できることが大きな特徴。
1日100〜200食という個人店舗に最適な生産量で、過剰投資にならない点も魅力です。
設置サイズは要確認ですが、比較的コンパクト設計。全国23拠点のアフターサポートがあり、導入後の安心感も抜群。
操作性も非常にシンプルで、初心者でも簡単に使える設計です。手打ち品質と操作性、サポート力のバランスが高く、安心感が強いことから4位にランクインしています。
5位:大成機械工業「タイセー」

参照:https://taisei-inc.jp/works/taisei/
大成機械工業の「タイセー」は、非常にシンプルな構造が特徴の製麺機。余計な機能を省き、操作のしやすさに特化しているため、機械操作に不安がある人でもすぐに使いこなせるのがポイントです。
耐久性も高いと評判で、長く使いたい個人店にはぴったり。サイズや生産量の詳細は公表されていないものの、少量から中規模まで柔軟に対応可能。
アフターサービスの明確な情報が少ない点と、デザインの古さが影響し5位としましたが、シンプル設計の魅力は非常に大きいです。
6位:品川麺機「製麺機」

参照:https://www.kitchen-t.co.jp/seimenki/product/mighty50/
品川麺機の「製麺機」は、省スペース設計ながら中規模店舗まで対応できる高い生産力が魅力です。
直感的な操作性が売りで、複雑な操作が不要な点は大きなメリット。厨房の狭い店舗でも無理なく設置できるのが強みです。
ただし、アフターサービスに関する情報が少なく、耐久性やメンテナンス性の詳細も明確ではないため、この順位。とはいえ、コンパクトで使いやすい製麺機を探している個人店には十分おすすめできる一台です。
7位:東北オーゼキ「小型機手打ち式製麺機」

参照:https://www.thk-ozeki.co.jp/service.html
東北オーゼキの「小型機手打ち式製麺機」は、手打ちの風味を重視するお店にぴったり。コンパクト設計で、厨房が狭い個人店舗にも設置しやすいサイズ感。
生産量は1日100〜150食ほどが目安。操作も簡単で、特に手打ちのコシや風味を求める方に支持されています。
オンラインでの修理相談や対応も可能なので、遠方の店舗でも安心。ただし、大手メーカーに比べると拠点数やサポート体制が少ないため7位。しかし、味にこだわりたい店には高評価の機械です。
8位:ソディック「製麺機」

参照:https://www.sodick.co.jp/product/food/noodle/
ソディックの製麺機は、本来工業用の高精度機械メーカーとして知られて、その技術力を生かした高性能な製麺機です。精度が高く、麺のクオリティは非常に優秀。
大量生産向けの機種が多いため、将来的に製麺所事業や複数店舗展開を見据えている人には有力候補。ただし、個人経営の小規模うどん店にはオーバースペック気味です。
価格も高めでメンテナンスコストも上がる点がネック。そうした理由から、ランキングは8位にしています。
9位:丸和製作所「製麺機」

参照:https://www.kitchen-t.co.jp/seimenki/product/400d_ss/
丸和製作所の製麺機は、堅牢性と高い耐久性で知られています。中規模店舗向けの生産量に対応し、長年使い続けることを前提とした設計が特徴。構造がシンプルで、基本的な操作は比較的容易です。
ただし、情報が少なく、最新機種の詳細や具体的なサポート体制が不透明。
特に、設置スペースの情報やメンテナンス性が分かりづらい点がランクを下げる理由です。それでも「長く使える安心感」が欲しい店舗には根強い人気があります。
10位:ワイズクラフト「小型製麺機」

参照:https://www.kitchen-t.co.jp/seimenki/product/mamezou/
ワイズクラフトの小型製麺機は、横幅わずか20cmという超スリムな設計が最大の魅力。厨房のわずかなスペースにも設置可能で、「とにかく場所を取らない製麺機が欲しい」というオーナーには最適です。
少量生産向けで、1時間150食程度が目安。直感的な操作性で、初心者でも扱いやすい点も高評価。ただし、生産量は限られるため、ランチのみ営業やテイクアウトメインの店舗向け。サポート面や耐久性の情報がやや不足するため10位にしています。
よくある質問(FAQ)
よくある質問を、以下にて詳しく紹介します。
- うどんとそば兼用機はおすすめ?
-
結論として、うどんとそばを同じ厨房で提供する場合、兼用機の導入は有効です。ただし、洗浄工程を徹底できる体制が整っていることが前提条件となります。
兼用機は、麺径の調整がしやすく、そば粉とうどん粉の切り替えも約1分で完了する利便性があります。しかし、アレルギー表示の観点からは、機械内部に粉が残らないように完全に洗浄する必要があり、通常より10~15分ほど余分に時間がかかるでしょう。
洗浄担当を固定することで作業の安定化を図り、約2週間でスムーズな運用が可能に。もしもピークタイム中に洗浄の時間が確保できない場合は、うどん専用機に加えて、別途小型のそば専用機を導入する方法も、安全面から推奨されます。
- 家庭用機との違いは?
-
家庭用と業務用の製麺機の違いは、連続稼働時間と部品の耐久性にあります。家庭用はモーターの定格が30分ほどで、ギアに樹脂製のものが多く採用。
一方、業務用はモーターが4〜8時間の連続稼働に対応し、ギアもステンレスや真鍮など頑丈な素材で構成されています。また、業務用は製麺幅が300mm以上あるうえに、切刃の交換もワンタッチで行える設計になっているため、作業効率も大幅に向上します。
たとえば「週末イベントで30食だけ提供する」といった用途なら家庭用も検討の余地はありますが、毎日ランチで120食を製造するような店舗では、業務用一択です。実際、知人のキッチンカー店では家庭用を使っていたところ、3カ月でモーターが焼き付き、修理費と営業停止で大きな損失を被る結果となりました。
- 導入後に失敗しやすいポイントは?
-
よくある失敗例として、次の3つが挙げられます。まず1つ目は、ミキサーの容量を見誤り、仕込みがピーク時間に追いつかなくなることです。
目安としては、1日の最大仕込み量の1.5倍の処理能力を持つ機種を選ぶと安心です。2つ目は、排水トラップの清掃を怠ってしまい、保健所の衛生チェックで減点されるケース。
実際の運用では、取扱説明書に書かれている頻度(月1回)よりも高い頻度(週1回程度)で清掃することを推奨します。3つ目は、万が一の故障時に備えたバックアップ手段がないこと。
乾麺のストックや、近隣の製麺所と緊急時の委託契約をあらかじめ結んでおくことで、営業への影響を最小限に抑えられます。
まとめ
業務用うどん製麺機は、単なる作業の自動化にとどまらず、コスト削減・味の安定・集客力アップ・商品差別化まで実現できる強力な武器です。
選定時には、対応する麺のタイプ、製麺能力、設置スペース、操作性、そしてサポート体制の5つのポイントをしっかり確認することが大切でしょう。
さらに導入後も、レシピの数値化やSNSでの発信を組み合わせることで、安定した運営と売上アップが可能になります。
この記事のランキングと導入ノウハウを参考に、ぜひ“儲かる自家製うどん店”への一歩を踏み出してみましょう。