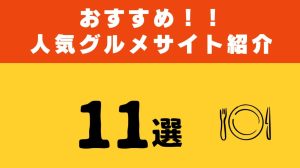「いつか自分のカフェを開きたい」
「おしゃれな空間で人を癒したい」
そんな夢を持ってカフェ開業に踏み出す人は少なくないでしょう。ところが、カフェは成功すれば華やか、失敗すれば“あっという間に赤字”という、非常にシビアなビジネスでもあります。
実際、中小企業庁の調査によれば、カフェを含む飲食業の3年以内の廃業率は約7割。
その理由に、家賃や人件費に対する売上バランスの難しい、集客戦略が甘い、利益構造が脆いなど、目に見えにくい経営の落とし穴が潜んでいます。
この記事では、潰れてしまうカフェの共通点と、逆に「選ばれるカフェ」として利益を出し続けるための成功戦略を余すことなく紹介します。
カフェは3年以内の廃業率が約7割と言われる
中小企業庁の「中小規模企業白書2023」によると、飲食業の廃業率は3年以内に約69.8%にのぼります。つまり、10人がカフェを開業しても、3年後に残っているのはたったの3人程度しかいないということです。
特にカフェは初期投資が比較的少なく、参入ハードルが低いため、思い切って開業する人も多い反面、経営に関する知識や戦略を持たないまま始めてしまうケースも少なくありません。
その結果、撤退も早く、「思っていたのと違った…」と
手を引いてしまうオーナーも多いのです。
参照:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
客単価・回転率が低く、利益構造が繊細
カフェ経営が難しい最大の理由のひとつは、利益構造が非常に繊細である点です。主な数字を見てみましょう。
- 客単価:都心部のカフェでは、1人あたりの平均消費額(客単価)は850円〜1,000円程度。
- 回転率:ランチタイムでも平均1.2回転、午後のカフェタイムに至っては0.8回転が一般的です。
- 原価率:ドリンクの原価率は30〜35%、フードは35〜40%といわれています。
これらの数値を見ると、多くの人が「え、それで家賃や人件費がまかなえるの?」と感じるはずです。
実際その通りで、売上設計やコストコントロールを甘く見ていると、すぐに資金繰りが行き詰まり、赤字に転落してしまいます。
特に都市部では家賃が高騰しているため、利益を出すどころか「毎月赤字で持ち出し状態」という店舗も珍しくありません。華やかな店構えの裏に、綱渡りのような資金繰りが隠れているのです。
カフェの平均的な売上と利益モデル
「カフェをやりたい!」と夢を抱く人は多いですが、現実の数字を知らずにスタートしてしまうと、高確率で赤字に陥ります。
まずは、一般的な街のカフェ(席数25~35席程度、住宅地寄りの駅近立地)を想定した平均的な売上・利益モデルを見ていきましょう。
| 指標 | 目安 | ワンポイント解説 |
| 客単価 | 約800~1,000円 | ドリンク中心の構成が一般的。スイーツや軽食を加えることで+200〜300円の単価アップも可能です。 |
| 1日来店者数 | 平均30~60人 | 駅近であっても、集客力やリピート施策次第で数字は大きく変動。土日に1.5倍を目指せるかがポイントです。 |
| 月商 | 約75~180万円 | 客単価×来店者数×営業日数(25日)で単純計算。閑散期と繁忙期でかなりの差が出ます。 |
| 粗利率 | 約65~75% | 原価目標はドリンク15〜25%、フードは30%以内に抑えるのが理想。仕入れの工夫とロス管理がカギになります。 |
| 月利益 | 約15~30万円 | 家賃・人件費の圧縮で初めて利益が残る構造。設備投資や広告費を含めるとさらに薄利に。 |
たとえば、客単価900円で1日50人来店×25営業日だと、月商は約112万円。粗利70%で約78万円。その中から家賃、人件費、水道光熱費、食材ロスなどが差し引かれ、残るのは月15〜30万円が一般的です。
夢の実現には、地に足をつけた利益設計が欠かせません。「どれだけ儲かるか」ではなく、「いくら残るか」を常に意識しましょう。生き残るカフェは、現実を冷静に見据えたお店です。
成功するカフェ8つの特徴
成功するカフェには、単に「美味しいコーヒーを出す」以上の共通点があります。立地や内装、メニュー構成、接客、運営体制からマーケティング施策まで、多角的に磨き上げられたポイントがあるからこそ、多くのお客様に支持され、継続的な売上と口コミを獲得できます。ここでは、成功するカフェの特徴を大きく8つの観点で解説します。
1. 明確なコンセプトとターゲット設定
コンセプトの一貫性は重要です。カフェの世界観やブランドストーリーを明確に打ち出すことで、来店動機を喚起します。例えば「〇〇産の豆にこだわる」「地元のアートを楽しむ場」「絵本が読める親子カフェ」など、他店と差別化できる軸が必要です。
ターゲットの絞り込みでは、年齢層・性別・利用シーン(仕事・勉強・デート・子連れ)を想定し、それに合わせたメニュー・席配置・営業時間を設計します。漠然と万人受けを狙うより、狙った層に愛される店づくりが成功の近道です。
2. 魅力的なロケーション選定
人通りと視認性は重要です。駅近やオフィス街の一角など、ターゲット層が日常的に行き交う場所を選ぶことで、ふらっと立ち寄る「ついで客」を獲得します。
また、周辺環境との調和も考慮しましょう。商業施設内や住宅街、公園近くなど、周囲の雰囲気に合わせた外装・看板デザインを採用し、「違和感なく街に溶け込む」ことも大切です。
3. メニュー開発と品質管理
主力商品の強化では、コーヒーなら豆の産地・焙煎度合い・抽出方法まで徹底したこだわりを持ち、これが評判となることでリピーターを増やします。
フードメニューの付加価値を行えば、自家製スイーツや軽食、季節限定メニューを提供し、ドリンクとの組み合わせで客単価をアップ。アレルギー対応やビーガン対応など、選択肢を広げることも顧客満足度向上に寄与します。
品質の安定化は、毎日の仕込み手順をマニュアル化し、
スタッフ教育や定期的なチェックで品質のばらつきを防ぎます。
4. インテリアと居心地の良さ
コンセプトに合わせた内装(北欧風、ヴィンテージ、ミニマルなど)を統一し、居心地の良さを追求。色彩や照明、家具の配置にもこだわり、写真映え(インスタ映え)を意識すると集客効果が高まります。
また、大テーブル、カウンター席、ソファ席、個室風ブースなど多様なニーズに応えられるレイアウトを用意。仕事や勉強、友人同士、デート、子連れなど、利用シーンに合わせた席選びができると親切です。
5. 心に残る接客とサービス
ホスピタリティ教育は重要です。笑顔と気配りを徹底し、常連客の名前や好みを覚えることで、特別感を演出します。
モバイルオーダーやセルフレジ導入、Wi‑Fi完備、充電コンセント設置など、現代の顧客が求める利便性を取り入れられます。
6. 効率的なオペレーション体制
バリスタの動きを分析し、動線を短くすることで提供時間を短縮。
売れ筋データを元に発注量を調整し、食品ロスを減らせます。
スタッフの役割分担も考慮し、ピークタイムの増員や多能工化トレーニングで、繁忙時にもサービス品質を維持します。
7. 継続的な集客・マーケティング施策
継続には、やはりデジタルマーケティングです。SNSでの情報発信(新メニューの告知、店内写真、バリスタ紹介など)や、Googleビジネスプロフィールの最適化で検索流入を確保。
ワークショップやミニライブ、地元作家の展示販売を行い、店を「場」として活用してもらうことで、新規顧客の獲得とリピート促進を両立します。
ポイントカードや会員限定キャンペーンを設定し、再来店を誘導できるでしょう。
8. 地域コミュニティとのつながり
地産地消の推進もおすすめ。地元食材や雑貨を取り入れることで、地域からの支持を得られます。
地域イベントへの参加では、フードフェスやマルシェへの出店で認知度を高め、帰路に立ち寄ってもらうきっかけを作ります。
潰れるカフェの7つの特徴
カフェ開業は「夢の実現」として多くの人が挑戦しますが、現実は甘くありません。どれだけ理想があっても、ビジネスとして成立しなければ継続はできないのです。
カフェを始めてから数々の壁にぶつかり、何度も「このまま潰れるのでは…」と冷や汗をかいた人も。
1. 立地が家賃優先で決定
「家賃が安いから郊外でもいいや」という選び方、実はかなり危険です。
人通りが少ない場所で固定費だけがかさみ、集客に苦しむパターン。
郊外の住宅街に店舗を構えたのはいいものの、平日の昼間は閑散。結果、広告費をかけて遠方から集客するという本末転倒な展開になった人もいます。立地は「安さ」ではなく「お客様が来るかどうか」で決めるべきです。
2. メニューが“なんでも屋
「幅広い客層を取りたい」と思い、
40品以上を出品し、失敗した店舗もあります。
パスタ、カレー、パンケーキ、サンドイッチ、スムージーなど何でもあり。結果、仕込みが膨大になり、スタッフのオペレーションも混乱。廃棄食材が月7万円にのぼり、利益率も15%まで低下した。などの事例もあります。
例えば、メニューを15品程度に絞り
「焼きたてホットサンド専門店」や「具だくさんスムージー&ボウル専門店」にするなどがおすすめです。
仕入れの商品が少なくなり原価率も改善し、オペレーションが簡易になることで調理時間も短縮できます。
3. 客単価設定が曖昧
「とりあえず800円くらいでいいか」となんとなく価格を決めていませんか。 客単価が曖昧だと、家賃や人件費をカバーできず、黒字化は難しくなります。
売上は「客数×客単価×回転率」。特にカフェは回転率が低いため、単価設定のミスが命取りです。後から原価や利益率を見直して、「この価格では全然足りない!」と青ざめた店舗様もよくお伺いします。
4. SNSを週1しか更新しない
「うちはSNS苦手だから…」というお店、意外と多いです。しかし今の時代、SNSは“看板”と同じ。更新頻度が低いと、存在すら知られずに終わります。週に1回しか投稿せず、フォロワーは全く増えず、集客にも結びつかない店舗もあります。
Instagramで毎日1投稿、週2回はリール投稿をして、
Instagram経由の新規来店が増えた店舗も。手間を惜しまないことが、命綱になります。
5. 原価と廃棄を把握していない
「今日も余ったからまかないに…」を続けていたら危険信号です。仕入れと売上のバランスが崩れ、利益がどんどん目減りします。「感覚」で発注していると、気づけば廃棄が月に何万円単位にも。きちんと毎週棚卸しをし、週次で原価率を計算するようにしてから、初めて「儲かる構造」が見えます。
6. スタッフ教育が属人的
オーナーや店長がいないと接客や味のクオリティが下がる店、よくありますよね。当店でも、ベテランスタッフが辞めた途端、ホール対応が崩壊し、レビューが急降下したことがありました。誰がやっても一定の品質を出せるよう、マニュアルや研修制度の整備は絶対に必要です。
7. リピート導線がない
「一度来たお客様がまた来る仕掛け」、ありますか。
ポイントカードやLINE公式アカウントなど、再来店を促す導線がないと、毎回新規顧客を集める必要があり、広告費がかさみます。
ある店も当初は何もなく、毎月新規頼みで疲弊していました。今では来店ポイントや、LINEでクーポン配布を行ったり、支払い時の接客を丁寧にすることで、リピート率が30%以上に改善した店舗もあります。
成功するカフェの黄金ロードマップ
カフェ経営は夢が詰まった仕事ですが、成功するには「感覚」や「勢い」だけでは難しいのが現実。潰れるカフェの多くが、最初の設計段階でつまずいています。
ここでは、実践に基づいた「成功の型」とも言える5つのステップを紹介します。このロードマップに沿って動けば、安定して利益を出すカフェを目指せます。
STEP1:コンセプト設計——ファン化の種を撒く
カフェの成功は、「誰のための店か」が明確であることから始まります。
- ペルソナを1人に絞る
→ たとえば「35歳・在宅ワーカーの女性」のように、具体的に設定すると内装やメニューにブレが出ません。 - キラーメニューを1つ決める
→ 目玉になる商品があると、SNSでも話題になりやすく、口コミが自然と広がります。 - 世界観を統一(内装・BGM・配色)
→ 写真映えや居心地の良さにつながり、リピート率も上がります。
STEP2:数字設計——儲かる構造を作る
感覚ではなく、数字から現実を逆算することがカフェ経営の基盤です。
- 売上 = 客単価 × 客数 × 回転率
【シミュレーション例】
- 目標月商300万円
→ 1日売上:約10万円 × 30日 - 客単価1,100円
→ 1日必要客数:約90人 - 座席数20席
→ 必要回転率:約4.5回
この計算により、「この家賃は高すぎる」「この席数では無理」といった見極めができます。開業前の時点で、無理な設計かどうかを明確に判断しましょう。
STEP3:マーケティング——集客の自動化
「良いお店を作れば人が来る」は幻想です。今の時代、ネットでの可視性が来店数を左右します。
1. SNS運用
- Instagram:毎日投稿+リール週2回でリーチ月4.5万件
- TikTok:店内DIY動画がバズり、週末の来店数が倍増した事例も
2. Googleビジネスプロフィール(GBP)
- 口コミへの返信率100%をキープすることでMAP上位に
- 実際にレビューが★4.6まで上昇し、広告費をかけずに新規顧客が増加。集客コストが20%減に。
3. リピート施策
- LINE公式×会員ID連携で、再来店率がアップ
- バースデークーポン配布で利用率12%を記録した事例も
一度来たお客様を逃さない「再訪の仕掛け」が、長期的な利益を支えます。
STEP4:オペレーション——属人化させない仕組み
スタッフのスキルに依存した運営では、安定したサービス提供が困難です。
- 標準作業手順書を動画で共有
→ 教育コストを大幅に削減し、誰でも即戦力に。 - 「3分以内提供チェックリスト」導入
→ 提供スピードが上がり、回転率が改善。 - POSレジ×原価管理システム連携
→ 食材ロスをカット。利益を守るためには、見えないコストの管理が重要です。
STEP5:財務&補助金——キャッシュアウトを防ぐ
売上が上がっていても、キャッシュがなければ続けられません。
- 開業時には日本政策金融公庫の低利融資を活用
→ 無理な自己資金投入を避け、安定した資金繰りを。 - 内装費には「小規模事業者持続化補助金」を申請
→ 最大100万円支給され、資金の余裕が生まれました。 - 月次決算&週次の資金繰り表の更新をルーティン化
→ この作業を怠ると、急な支出に対応できず、経営が傾きます。
カフェ経営は「センス」や「雰囲気」だけでは勝てません。数字・仕組み・導線の3本柱をどれだけ戦略的に設計できるかが成功の分かれ道です。
このロードマップに沿って準備を進めれば、「潰れないカフェ」ではなく、「選ばれるカフェ」になれるはずです。夢を夢のままで終わらせないために、ぜひ参考にしてください。
フードデリバリー・テイクアウトの導入も選択肢に
カフェ運営で来店数や売上の伸び悩みを感じているなら、フードデリバリーやテイクアウトの導入は大きな打開策になります。
特に席数が限られていたり、オフピークの時間帯が空いている店舗では、固定費を変えずに売上を上乗せできるチャンスです。
店内が空いている時間帯こそ、新しい売上チャンス。テイクアウトも組み合わせながら時間ごとのメニュー戦略を立てていきましょう。
Uber Eatsを始めたい、もっと売上を伸ばしたい…
でも、「何から手をつければいいかわからない」 というお店も多いのではないでしょうか?
実際、Uber Eatsはただ導入するだけでは成功しません。「適切な設定」「効果的なメニュー設計」「売上UPの戦略」 が重要になります。
しかし、独学で試行錯誤するのは時間がかかるし、リスクも大きい…。
そんなお悩みを解決するのが、私たちの無料サポートです!
弊社は Uber Eatsの一次代理店 として、これまで 2000店舗以上 の導入を支援してきました。その経験をもとに、「売れるお店」が実践しているノウハウ を無料で提供しています!
- 導入前の相談 → Uber Eatsのメリット・デメリットをわかりやすく解説!
- 初期設定のサポート → 効果的なメニュー設定&価格戦略をアドバイス!
- 売上UPの戦略提供 → 注文数を増やすプロモーションや運用のコツを伝授!

Uber Eatsの導入・売上UPサポートはすべて無料!
まずはお気軽にご相談ください!

よくある質問(FAQ)
よくある質問を紹介します。
- 小規模でも自家焙煎はコスパ悪くない?
-
焙煎機は中古で60万円〜。豆の仕入れ原価を40%下げられるので1年で回収できました。
- フリーWi-Fiは回転率を下げるのでは?
-
長居客が増える一方、客単価も+150円(追加ドリンク)になり、売上はむしろ上がりるケースもあります。
- テイクアウト専門と迷っています
-
家賃を抑えられる一方、客単価が下がりがち。イートイン8席+テイクアウト併用モデルがバランス良いでしょう。
まとめ
カフェ経営は、決して「センス」や「こだわり」だけで成り立つ世界ではありません。現実には、数字の設計、オペレーションの仕組み化、集客戦略の継続、そして何より「顧客に選ばれ続ける仕掛け」が必要です。
この記事で紹介したように、潰れるカフェには明確な共通点があり、成功するカフェには再現性のある「型」が存在します。たとえ今、経営がうまくいっていなくても、見直すべきポイントを一つずつ整えていけば、黒字転換は決して不可能ではありません。
夢だけで終わらせないために、そして「いつか」ではなく「ちゃんと」儲かるカフェを実現するために。あなたのお店に合った戦略を見つけ、地に足のついた経営を目指していきましょう。成功は、戦略と行動の先に必ずあります。