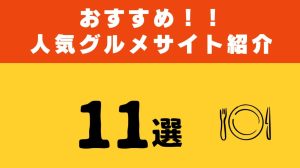居酒屋は「儲かるけれど潰れやすい」と言われる業態です。集客が安定すれば高い売上が期待できる一方で、家賃や人件費、原価の高騰といったコストの負担が大きく、適切な経営判断を誤れば簡単に赤字へ転落してしまいます。
実際に、中小企業白書のデータでも、飲食業の約4割が開業から3年以内に廃業しているという現実が。
しかし、正しい損益管理と現代のマーケティング戦略を駆使すれば、安定的に利益を生み出すことは十分可能です。
そこでこの記事では、潰れる居酒屋に共通する7つの失敗する理由と、それを回避するための成功法則、さらには最新のマーケティング戦略まで、具体例を交えながら詳しく紹介します。
居酒屋は「儲かるが、潰れやすい」業態
居酒屋は一見「儲かる」と思われがちですが、実際には非常にリスクの高い業態です。一方、売上は比較的作りやすいビジネスです。1卓あたりの客単価に回転数を掛け合わせることで、一定の売上期待は計算できます。
例えば、都内で運営していた20坪の店舗では、月商600万円を達成していましたが、営業利益率はわずか6%。つまり、利益は月に36万円しか残らず、家族を養っていくには決して安心できる数字ではありませんでした。
さらに、居酒屋業界は非常に撤退率が高いことでも知られています。飲食業全体の3年生存率はわずか約30~40%。
開業から3年以内に4割ほどが撤退しています。
また、収益性は店舗の立地や規模によって大きく変わります。都市部では安定した集客が見込める反面、家賃や人件費の高騰が利益を圧迫。一方、郊外では家賃が安いものの、しっかりとした集客チャネルを持たなければ、閑古鳥が鳴いているお店も少なくありません。
居酒屋ビジネスの損益分岐をざっくり試算
居酒屋の経営において、まず最初に知っておくべきなのが「損益分岐点」です。ざっくりと算出するためには、月ごとにかかる固定費と売上に応じて増減する変動費を明確にすることが必要です。
そのうえで、変動費比率(売上高の中で、変動費が占める割合のこと)を計算し、「損益分岐点売上高 = 固定費÷(1ー変動費比率)」という公式を使って、赤字にならないために必要な最低売上高を導き出します。
損益分岐点の出し方
- 固定費の算出
家賃、人件費、光熱費、減価償却費など、売上に関係なく毎月発生する費用の合計。 - 変動費の把握
食材費や消耗品費など、売上に比例して増減するコストを計算。 - 変動費比率の算定
計算式は「変動費÷売上×100」。これが変動費比率になります。 - 損益分岐点売上高の計算
「損益分岐点売上高 = 固定費÷(1ー変動費比率)」で求めます。
試算の具体例
- 月の固定費:100万円
- 売上100万円に対する変動費:50万円
この場合、変動費比率は「50 ÷ 100 × 100 = 50%」。
損益分岐点の売上高は「100万円 ÷ (1-0.5) = 200万円」。
つまり、月に200万円以上売り上げなければ、経営は赤字になるという結果です。
合わせて考えるべきポイント
- 客単価
1人のお客様が平均して支払う金額。単価が高いほど目標売上に近づきやすい。 - 回転率
1日あたり、1つの席が何回利用されるかの目安。回転率を上げれば売上も増加。 - 原価率
売上に対する仕入れコストの割合。原価率を抑えれば、粗利が改善される。
こうした要素を組み合わせて詳細な損益分岐点をシミュレーションすることで、より実現性の高いビジネスプランを立てることが可能になります。
収益の決まり方
居酒屋の収益は「営業スタイル×人件費管理×客単価」のバランスで決まります。平均客単価は3,000〜4,000円、月商は100万〜600万円が一般的で、オーナー年収は約300万〜800万円が目安。利益は「客単価×客数×営業日数-経費」で算出。
経費は原価(フード30%、ドリンク20%)、人件費(売上の25%以内)、家賃(売上の10%以内)など。例えば40席・回転率1.5回なら月商は約525万円、経費75%を引くと月利益131万円、年収は600〜800万円が現実的なラインです。
潰れる居酒屋の7つの共通点
居酒屋は儲かりそうに見えて、実は飲食業の中でも最も撤退率が高い業態のひとつです。中小企業白書や各種調査でも示されている通り、開業から3年以内に約4割が廃業しています。
都内で複数の店舗を経営する中で、うまくいった店もあれば、閉めざるを得なかった店も経験した人も。
なぜ潰れるのか?その理由には明確な共通点があります。この章では、実体験とデータから導き出した「潰れる居酒屋の7つの共通点」について、具体的な事例とともに紹介します。
1. 賃料比率が売上の10%を超えている
立地は居酒屋の生命線。しかし、だからといって家賃が高すぎるのは致命的です。
目安となるのは「賃料は売上の10%以内」。これを超えると、ほんの少し売上が落ちただけでも経営が一気に苦しくなります。
ある過去に閉めた1店舗は、駅徒歩1分の好立地。確かに昼も夜も人通りは多かったのですが、家賃が売上の18%を占めていました。繁忙期はよくても、梅雨や真夏などの閑散期に即赤字。高立地=安定ではなく、ハイリスクハイリターン。場所の良さを過信せず、家賃が適正か冷静に判断する必要があります。
2. 原価率40%超えのまま放置する
飲食店の適正な原価率は30〜35%が目安。しかし、よくあるのが「これは看板メニューだから」と、原価40%を超えても価格改定できない店。
たとえば、ある居酒屋では、名物の刺身盛り合わせの原価率が50%を超えていました。「これを目当てに来てくれているから値上げできない」という理由で値段据え置きを続けました。でも結果は、利益が削られ続け、最終的に閉店。
原価が高騰する時代に、「名物だから変えられない」は経営破綻のもと。お客様の満足度を守りながらも、提供サイズの調整、メニューの構成変更、期間限定化など、利益を守る工夫が必須です。
3. 客単価が低いのに回転率も低い
これは非常に多い失敗パターンです。
- ドリンク一杯で2時間居座る
- 食べ放題・飲み放題で薄利多売
- 学生向けの低単価メニュー中心
こうなると、「安くて長居」の悪循環。そもそも、居酒屋のビジネスモデルは「客単価 × 回転数」で成り立っています。
回転率が低いのに低価格設定のままだと、売上はまったく伸びません。成功した店舗では、「0次会専門」「立ち飲みで1時間以内」といった時間軸を意識した設計を導入。
結果的に客単価は2,500円と安くても、2時間で3回転できることでしっかり利益が出ました。
ターゲット設定とサービス設計は経営の生命線です。
4. 人件費が25%を超えている
飲食店経営において、人件費は最大のコスト。売上に対して25%以上の人件費がかかっている場合、かなり危険です。
典型的なのは、「忙しくなったらすぐに人を増やす」パターン。これでは売上の波に耐えられません。
ある店舗では、セントラルキッチン方式を導入。仕込み作業を本店に集約し、各店舗のオペレーションを簡素化。結果、人件費率は22%まで改善。
キッチンの簡略化、セルフオーダーシステムの導入、メニューの絞り込みなど、「人が少なくても回る仕組み」をつくることが生存戦略になります。
5. コンセプトが曖昧すぎる
「なんでもあります」の居酒屋は、今の時代ほとんど選ばれません。
たとえば、メニューに「焼き鳥」「寿司」「パスタ」「韓国チヂミ」が並んでいる店。お客さんは逆に「結局この店は何が得意なの?」と困惑します。
今の消費者は、GoogleやSNSで「目的買い」する時代。日本酒好きなら「日本酒専門の居酒屋」、一人飲みなら「0次会特化」、女性客なら「韓国風おしゃれバル」など、一点突破の明確なコンセプトがなければ選ばれません。
ぼんやりした店は、最初の一回は入っても二回目はありません。
6. SNS・レビューサイトを無視している
今や、Googleマップの評価や食べログ、インスタグラムの存在感は無視できません。あなたの店の評価が★3.0を切っている場合、新規のお客様の多くは候補から外します。
立て直しに成功した店舗では、「Googleレビューの返信を全件実施」「SNS週3回投稿」を徹底。結果、マップ検索からの来店が2倍に増加しました。
- メニュー写真を定期的にアップ
- クチコミには必ず丁寧に返信
- イベントや限定メニューの発信
ネット上の「顔」を放置するのは、リアル店舗で看板を出さずに営業するのと同じ。SNSとレビューは無視できない集客装置です。
7. キャッシュフローを管理していない
居酒屋経営で最も怖いのが、「黒字倒産」。売上は順調でも、現金が足りずに店を閉める事態です。
理由は簡単。売上が入るタイミングと、仕入れや家賃の支払いタイミングのズレ。
月末の家賃、翌月の食材費、給与…まとまったお金が一気に出ていきます。ここを甘く見ると、あっという間に資金ショート。
- 今週の入金と出金
- 来週の支払い予定
- 1ヶ月先の資金余力
これを常に確認しておくことで、急な売上低下にも耐えられます。
成功する居酒屋の5つのポイント
飲食業界は常に厳しい競争の中にあります。特に居酒屋は、流行の波や景気の影響を受けやすく、撤退率も高い業態です。しかし、その一方でしっかりとした戦略と工夫を積み重ねれば、安定して利益を出し続けることも可能です。
ある店舗で、都内で複数の居酒屋を経営し、失敗も成功も数多く経験してきました。その中で、「成功している店舗には共通の法則がある」ことに気づきました。
ここでは、実際の成功事例を交えながら、「成功する居酒屋の5つのポイント」を徹底解説します。
1. 「誰に・何を・いくらで」を一点に絞る
まず一番大事なのがターゲットとコンセプトの明確化です。誰に向けて、何を、どの価格帯で提供するのかを、徹底的に絞り込むことが成功のカギになります。
ある店舗は「クラフトサワー専門」というコンセプトに振り切りました。内装もナチュラルテイストに変更し、カラフルなサワーが映えるよう照明も工夫。結果、女性のお客様が7割を占めるようになり、客単価は3,800円から4,600円へと約20%アップしました。
ポイントは、「居酒屋=なんでも屋」を脱すること。たとえば、
- 日本酒特化の居酒屋
- 0次会専用の立ち飲み
- チーズ料理メインのバル
- 韓国料理×映えドリンク
など、尖ったコンセプトほど、今の時代の消費者には刺さります。メニューも「選ばせる」のではなく、「これがウリです」と押し出すことが大切です。
2. 原価率と人件費を日次でチェックする
売上ばかり見ていても、実際の利益は見えてきません。居酒屋経営の利益管理で重要なのは、FL比(原価率と人件費の合計)をリアルタイムで把握すること。
GoogleスプレッドシートとLINEを連携し、スタッフ全員が毎日数字を確認するのはおすすめです。
具体的な運用例
- スプレッドシートに「売上」「原価」「人件費」を日次入力
- 朝礼時に全員に共有(LINEでも営業終わりに共有するのもありです)
- 前日データを見て「昨日は〇〇が多かったから人件費が高かった」「原価が上がっているからメニューの見直しをしよう」と即時フィードバック
この仕組みを導入した結果、3ヶ月でFL比が60%から48%に改善した店舗もあります。
この数値を毎日意識するだけで、経営の質が圧倒的に上がります。
3. 売上チャネルを3本持つ
一つの売上だけに頼るのは、今の時代、極めてリスクが高いです。特にコロナ禍以降、その重要性が顕著になりました。以下の3本柱を参考にしましょう。
■ STEP1:店内飲食
→ メインの売上源。コンセプトを明確にし、安定した客数を確保。
■ STEP2:テイクアウト・デリバリー
→ 店舗の味を自宅でも楽しんでもらう。Uber Eatsやmenuを活用。
■ STEP3:物販・EC
→ 自家製レモンサワーのシロップや、オリジナル調味料をオンラインで販売。
今や「飲食店=飲食だけ」ではなく、体験×商品×オンラインの組み合わせが新しいスタンダードです。
4. ファン化施策を徹底する
1回来たお客様を、「ただの一見さん」ではなく「常連ファン」に変える仕組みが、利益の安定には欠かせません。
具体的な施策例
- LINE公式アカウントでスタンプカード
→ 5回来店でドリンク1杯無料など。 - Instagramのリール動画で新メニュー発信
→ SNS経由の新規来店が月30組以上。 - 月1回の常連限定イベント
→ 日本酒飲み比べ会、推しのサワー総選挙など。
効果の数値
リピート率が導入前の26%から41%に上昇。来店頻度が上がることで、広告費をかけずに売上が伸びる好循環が生まれます。SNSは「集客の入り口」、LINEは「ファンとの関係を深めるツール」として役割分担。リアルとデジタルの両輪で回すことが成功のポイントです。
5. 「辞め時」を決めておく
意外に思うかもしれませんが、成功する店ほど「撤退ライン」を明確に設定しています。
例えば、次のようなルールを設けてみるのもいいでしょう。
- 3ヶ月連続で営業利益がマイナス5%を超えたら撤退検討
- 月間売上が最低ラインの70%を3ヶ月続けて割ったら業態変更
このルールを持つことで、ズルズル赤字を続けることなく、早期の撤退→次の挑戦へ素早くシフトできます。
さらに、「閉める基準」があることで、現場スタッフにも「今ここが踏ん張りどころだ」という危機感と目標意識が生まれます。
撤退=失敗ではありません。むしろ、「戦略的撤退は成功の一部」という考え方が、経営者には不可欠です。
地域・店舗規模による収益性の違い
居酒屋の経営は、立地や店舗規模によって収益性が大きく左右されます。都市部と郊外・地方では、それぞれにメリットとデメリットがあり、成功のための戦略も大きく異なります。ここでは、両者の特徴と勝ち筋について詳しく紹介します。
都市部の強みと落とし穴
まず、都市部での居酒屋経営の最大の強みは圧倒的な集客力です。昼も夜も人通りが多く、オフィス街ならランチ需要、繁華街なら夜の飲み需要が安定しています。また、客単価も上げやすく、質の高い商品や空間を提供することで、プレミアム価格でも支持されやすいのが特徴です。
しかしその一方で、都市部ならではの高コスト構造が大きなリスク。家賃は郊外の数倍、人件費も高騰しています。さらに競合店も非常に多いため、差別化ができなければ埋もれてしまう可能性が高いです。
成功するための具体的な戦略としては、「ランチ営業の撤退+夜営業への集中」がおすすめです。昼間は人件費の割に利益が出にくいケースが多く、無理にランチ営業をするよりも、夜の営業に全リソースを集中し、回転率と客単価を最大化することで、家賃分の回収スピードを上げることができます。
郊外・地方の強みと落とし穴
一方、郊外や地方の居酒屋経営は、都市部とは真逆の特徴を持ちます。まず大きな強みは、固定費が圧倒的に低いこと。家賃も人件費も都市部の半分以下というケースは珍しくありません。
さらに、駐車場がある店舗が多いため、ファミリーやグループ客を取り込みやすく、客単価も意外と高く設定できるのがポイントです。
ただし、郊外には特有のリスクも存在します。まず、需要の波が非常に極端です。土日や夜は満席になる一方で、平日の昼間はガラガラということも珍しくありません。
また、都市部のように「偶然通りがかったから入る」という流動客が少なく、口コミや地域の評判への依存度が非常に高い傾向があります。
このような環境下での成功のカギは、ファミリー向けのメニュー開発と宅配・テイクアウトへの積極対応です。お子様セットやシェアメニューを用意し、ファミリー層をターゲットにすることで平日の利用も促進可能でしょう。
また、宅配サービスを導入することで、自宅飲み需要を取り込むことができ、閑散時間帯の売上補填にも繋がります。
儲かる居酒屋に変えるためのマーケティング戦略
居酒屋の売上を安定させ、さらに伸ばすためには、従来の集客だけでなく、「今の時代に合ったマーケティング戦略」が不可欠です。
ここでは、効果実証済みの5つの具体的な施策をご紹介します。
1. Googleマップの口コミ対策(MEO強化)
今や予約の約6割はGoogle経由。地図アプリで店を探す人が急増しています。実際に、口コミの星が3.8から4.2に上がるだけで、クリック率は約1.7倍に跳ね上がるというデータも。
星4.0以上を目指すには、①料理名付きの写真を毎週3枚投稿、②会計時に口コミ依頼の一言+QRコード設置、③★3以下の評価には24時間以内に具体的な改善策を添えて返信。
この対策により、横浜の串焼き店ではGoogle経由の予約が月18件から68件に増加。広告費ゼロで月43万円の売上アップに成功しました。
2. LINE公式アカウント活用でリピート率UP
LINE公式アカウントを活用したリピート施策は、極めて高い効果があります。客単価4,000円、月間来店数1,500人の店なら、リピート率が1%上がるだけで年間360万円の売上増。
具体策は、①友だち登録でドリンク1杯無料、②登録後に誕生日クーポン(20%OFF)を自動配信、③ポイント5つで飲み放題30分延長。札幌の「SAKE BAR HACHI」では、LINE友だちが3,200人に。
誕生日月の再来店率は35%から62%へ上昇し、年間売上は820万円もアップしました。
3. 女性・ファミリー向けメニューで平日集客
週末は満席でも平日がガラガラ…そんな課題には、女性客やファミリー層向けのサービスが効果的。例えば、低アルコールやノンアルカクテルを10種類以上用意し、ハーフサイズのサラダやデザートで「頼みやすさ」をアップ。
さらに、子ども向けのワンコインセット(うどんor唐揚げ+ドリンク)も導入。東京・立川の「大衆酒場 こはち」では、平日17〜19時を「ママ割タイム」と設定し、女性ドリンク半額+ファミリー向けの座席を強化。結果、平日の売上が54%も向上しました。
4. 食べログ・ホットペッパーは「保険」で使う
高額な掲載料がかかるポータルサイトは、今や「集客の保険」と割り切るのが正解。
コツは、①有料プランはやめて無料+単発クーポン掲載にする、②写真はTOP3枚だけプロカメラマンを使って高品質に、③クーポンは曜日や時間帯を限定して、常連客の値引き依存を防ぐこと。
5. Instagramとショート動画で世界観を伝える
SNS時代の集客では、Instagramの活用がカギ。特にZ世代では、インスタ検索がGoogleを超えるほどの影響力。
ポイントは、①7秒以内の調理シーンをトレンド音源に乗せて毎週2本投稿、②スタッフの素顔や裏側を発信し「推し店員」を作る、③「#エリア名 #業態 #料理名」などのハッシュタグを固定すること。
名古屋の「肉バルUNO」では、この戦略でフォロワーが4,500人から11,000人に急増。「インスタ見ました」の予約が月15件→96件に増え、映える炙りチーズ動画は42万回再生。結果、月商は120万円アップしました。
実際に成功している居酒屋の事例紹介
近年、居酒屋の集客成功事例として注目されているのが、SNSによる情報発信の強化と、インフルエンサーとのコラボレーションです。
たとえば、「酒場リベリー episode2」は、SNS運用を積極的に行い、若年層の顧客獲得に大きく成功しています。さらに大手回転寿司チェーンのスシローは、人気YouTuberとのタイアップで話題を集め、多くの集客効果を生み出しました。
これらの事例から共通して言えるのは、独自の世界観や魅力的なメニュー作りに加え、SNS発信とインフルエンサー活用が現代の集客における強力な武器だということです。
事例1|酒場リベリー episode2
この店舗は、創作天ぷらとイタリアンの融合という一風変わったコンセプトを掲げ、大衆酒場の新たな形を提案しています。ターゲットは特に20〜30代の女性。SNS映えを意識したビジュアル重視のメニューが特徴です。
特に、看板商品である創作天ぷらは、食材選び、ユニークなネーミング、そして独自のソース使いまで細部にこだわり、SNS上で自然に拡散される仕組みを作っています。
さらに、カラフルなフルーツサワーも大ヒット。Instagramを中心に口コミが広がり、フォロワー数は6,000人を突破。結果として、坪月商は57万円という高水準を実現しています。
事例2|スシロー×きまぐれクック
大手寿司チェーンのスシローは、人気の魚さばき系YouTuber「きまぐれクック」とコラボレーションを実施。彼の動画内で取り上げられた料理「カンジャンケジャン(ワタリガニの醤油漬け)」を商品化しました。
この動画が公開されると、視聴者の間で一気に話題となり、スシロー店舗での注文が爆発的に増加。動画を見たファンが、「自分もあの料理を食べてみたい」という強い購買動機を持って来店する流れが生まれたのです。
この成功のポイントは、YouTuberの持つ発信力と信頼性をダイレクトに店舗集客へつなげたこと。オンラインの体験がオフラインで実現できる仕組みが、大きなバズを生み出しました。
フードデリバリーやテイクアウト導入も検討を
フードデリバリーも検討を!
夜営業だけでは不安定な時代に
現在、多くの飲食店が直面しているのが「夜営業依存による不安定な収益構造」です。特に、飲み会文化の縮小により、「金・土だけ混雑、平日は閑散」という店舗が増加中。
こうした流れに対応するために、デリバリーやテイクアウトを活用した収益の分散が求められています。
導入のメリットは、次の通りです。
- 時間帯による収益の分散
- デリバリー注文のピーク:18〜20時
- テイクアウトは12時台のランチ需要にも対応可能
- 客席数に依存しない売上確保
- 店内の回転率に関係なく販売可能なため、
- 「追加の人件費 < 売上増加分」となりやすい
- 実績例
- ある小規模店舗(20席)では、Uber Eats導入後の月商が+28万円。
仕込み時間中に完結させたため、人件費の増加はわずか「+2万円」でした。
- ある小規模店舗(20席)では、Uber Eats導入後の月商が+28万円。
Uber Eats、menu、出前館への出店手順と手数料比較
フードデリバリー市場が急成長する中で、飲食店にとって「店外収益の確保」は重要なテーマになっています。なかでも、Uber Eats・menu・出前館は代表的なプラットフォームであり、出店を検討する際の選択肢として広く利用。ここでは、出店の流れと手数料について、それぞれのサービスを比較しながら紹介します。
出店初期コストの違い
| サービス名 | 通常時の初期費用 | 実際の現在価格 |
| Uber Eats | 約5万円 | 無料(プロモーション中) |
| menu | 約5万円 | 無料(キャンペーン適用) |
| 出前館 | 約2万円 | 無料(期間限定) |
まず、各サービスで出店する際にかかる初期費用について見てみましょう。現在はキャンペーン実施中のサービスが多く、ほとんどが無料でスタート可能な状況です。
また、いずれのサービスでも月額の固定料金は発生しないため、リスクを抑えて参入可能です。
手数料の比較
| サービス名 | モデル別 | 費用・条件 |
| Uber Eats | 購入型 | 約22,500円(買い切り) |
| menu | Wi-Fi版:15,000円セルラー版:20,650円+売上の3%(上限1,100円) | 一部月額連動あり |
| 出前館 | Wi-Fi:月額1,200円セルラー:月額2,000円 | 月額レンタル方式 |
デリバリーサービスを利用するには、注文受信用のタブレットが必要となるケースがほとんどです。なお、menuに関しては売上に応じた追加課金が発生するため、費用面で複雑さがあります。
飲食店の集客にフードデリバリーが使える!
Uber Eatsや出前館などのフードデリバリーサービスに登録すると、アプリ内でお店がリストに載ります。お客様はアプリを開いて、近くのお店を探しているだけでも「この店いいじゃん!」ってなることが。たとえば、「ピザが食べたいな〜」ってアプリで探してたら、今まで知らなかったお店が目に入ることがよくあります。お店に行くハードルが下がるし、ちょっとした宣伝にもなるんです。
特に、忙しくて外に出られない人や、「新しいお店を試してみたいな〜」と思ってる人が、フードデリバリーを利用することが多いんです。だから、普段は来ないようなお客様にもお店を知ってもらうチャンスが増えます。
弊社では、飲食店をはじめるなら無料で使えるUber Eatsは導入必須のマーケティングツールでもあると考えています!
Uber Eatsを始めたい、もっと売上を伸ばしたい…
でも、「何から手をつければいいかわからない」 というお店も多いのではないでしょうか?
実際、Uber Eatsはただ導入するだけでは成功しません。「適切な設定」「効果的なメニュー設計」「売上UPの戦略」 が重要になります。
しかし、独学で試行錯誤するのは時間がかかるし、リスクも大きい…。
そんなお悩みを解決するのが、私たちの無料サポートです!
弊社は Uber Eatsの一次代理店 として、これまで 2000店舗以上 の導入を支援してきました。その経験をもとに、「売れるお店」が実践しているノウハウ を無料で提供しています!
- 導入前の相談 → Uber Eatsのメリット・デメリットをわかりやすく解説!
- 初期設定のサポート → 効果的なメニュー設定&価格戦略をアドバイス!
- 売上UPの戦略提供 → 注文数を増やすプロモーションや運用のコツを伝授!

Uber Eatsの導入・売上UPサポートはすべて無料!
まずはお気軽にご相談ください!

まとめ
居酒屋経営は決して楽な道ではありませんが、「数字に強くなること」と「現代の集客方法を理解すること」で、十分に勝てるビジネスです。
賃料や人件費、原価管理の徹底に加え、LINEやInstagramを使ったファンづくり、Google口コミの活用、さらにはテイクアウトやデリバリーを組み合わせることで収益の安定化も図れます。
さらに、撤退ラインを事前に決めておくことで、リスクを最小限に抑えつつ次の挑戦にもつながります。今の時代に合った正しい経営とマーケティングを実践すれば、居酒屋は「潰れるビジネス」ではなく、しっかり儲かるビジネスに変わるのです。