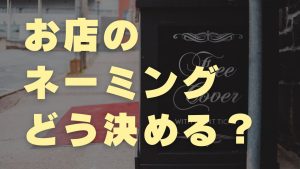飲食店でお客さんに選ばれる理由は、味や内装の良さだけではありません。「なんとなく気になる」「一度行ってみたい」と思わせる小さな工夫があるかどうかで、集客力は大きく変わります。その工夫の一つが「ずらし系コンセプト」。
定番の業態やメニューに半歩だけひねりを加えることで、他店にはない魅力を生み出せる手法です。
この記事では、実際の成功事例をもとに5つの「ずらし系」パターンと、効果的な店名の決め方を解説します。さらに、失敗から学ぶリネームの実例や実装チェックリスト、よくある質問まで網羅。
これからお店を開く方はもちろん、既存店のリブランディングを考えている方にも役立つ内容です。
「ずらし系」コンセプトとは
「ずらし系」とは、すでにあるアイデアや商品にちょっとした工夫を加えて、新しい魅力を生み出す考え方です。
まったく新しいものを作るのではなく、身近なものを“少しずらす”ことで分かりやすさとオリジナリティを両立できるのが特徴です。
たとえば、普通のおにぎり屋さんなら「鮭」や「梅」が定番ですが、「夜はおにぎりとお酒を楽しめるバー」として提供すれば、一気に新しいスタイルのお店に変わります。
カフェでも「昼はコーヒー、夜はワインを出す」と工夫することで、同じ場所でも異なるシーンに対応できます。
ポイントは、大きく変える必要はないということです。時間帯を変えたり、対象のお客さんを少し変えたりするだけで、他のお店にはない魅力が生まれます。
競合が多いジャンルほど、この「ずらし系」の発想が効果的で、自然に話題性や特別感を出せるのです。
なぜ「ずらし系」が効果があるのか
お店のコンセプトや名前を考えるときに役立つのが「ずらし系」という考え方です。
これは、まったく新しいことを始めるのではなく、既存のアイデアにほんの少し工夫や意外性を加えることで、お客さんの目を引く方法です。
ここでは、どうして「ずらし系」が効果を発揮するのかを分かりやすく紹介します。
「食べた後の評価」と「お店を選ぶ前の印象」
飲食店で一番大切なのは「料理の味」ですが、お客さんが実際に来店するかどうかを決めるのは、その前の段階です。
SNSやGoogleマップで検索しているとき、お客さんはまだ一口も食べていません。その状態で「このお店に行こう」と判断するわけです。特に同じようなジャンルのお店が並ぶエリアでは、第一印象で勝負が決まることも少なくありません。
そこで「ずらし系」の考え方が役立ちます。たとえば「朝だけ営業するカレー屋」や「夜はおにぎりを出すバー」など、ほんの少し他と違う仕掛けを加えるだけで、「ちょっと気になるから行ってみたい」と思わせるきっかけになるのです。
行列店の共通点
人気があるお店には、必ず「話題にしたくなる要素」があります。たとえば「純喫茶なのにビーガン料理専門」とか「注文してから精米するご飯屋さん」といった、意外でユニークな工夫が口コミにつながります。
さらに、店名も重要なポイントです。行列ができるお店ほど、名前が短くリズムよく、3〜6文字程度で口に出しやすいものが多いです。覚えやすく、SNSや検索でもヒットしやすいため、お客さんが自然に広めてくれる流れを作れるのです。
つまり「語りたくなるネタ」と「覚えやすい名前」が揃うことで、口コミが広がりやすくなります。
ありがちな失敗パターン
一方で、うまくいかないケースもあります。代表的なのは、無難にフレームワーク通りに作ったコンセプトです。確かに安全ではありますが、個性が弱く、他店に埋もれてしまう可能性が高いのです。
また、数字やデータに寄せすぎて「どこにでもあるようなお店」になってしまうのも失敗の原因です。さらに、店名が長すぎたり読みづらい名前だと、検索されにくいだけでなく、口コミでも広がらず、電話予約で間違えられることも増えてしまいます。
だからこそ、店名はシンプルで覚えやすくすることが大切です。そのうえで、半歩だけ他と違う「ずらし」を加えることで、競争の中から抜け出しやすくなります。
飲食店で使える3つのずらし系コンセプト
飲食店の競争が激しい今の時代、味や価格だけで差別化するのは簡単ではありません。そんなときに有効なのが「ずらし系」の発想です。
ずらし系とは、定番の枠組みから少しだけ視点をずらし、意外性や新鮮さを生み出す工夫のこと。
ここでは、特に効果的な「ターゲット」「シチュエーション」「時間帯」という3つの切り口から考えるずらし系コンセプトを紹介します。
1. ターゲットをずらす
多くの飲食店は「幅広いお客さん」をターゲットにしがちですが、あえて狭めることで逆に強い魅力を発揮できます。例えば「30代女性限定ランチ」や「子連れママ専用カフェ」は、特定の層にとって強い共感を呼びます。
ターゲットを絞ると宣伝メッセージも明確になり、口コミも広がりやすくなります。「働く30代の女性に、野菜たっぷりでヘルシーな夜定食を」など、具体的なペルソナを描くことで、同じ属性の人に強烈に刺さるお店に変わります。結果的に「自分のためのお店」と感じてもらえるため、リピートにつながりやすいのです。
2. シチュエーションをずらす
「食事をする」という行為は、時間帯や場所だけでなく、利用目的によっても大きく印象が変わります。例えば「仕事終わりのリラックス空間」や「読書専用カフェ」のように、シチュエーションを想定して演出するのがずらし系の工夫です。
たとえばラーメン屋で「打ち合わせOK!Wi-Fiと電源完備」を打ち出せば、オフィスワーカーの会議利用が増えます。
また、「夜は静かに一人で晩酌できる蕎麦屋」といったコンセプトなら、同じメニューでも全く違う価値が生まれます。つまり、食事そのものではなく「どんな場面で使えるか」を明確に提示することが、シチュエーションのずらしです。
3. 時間帯をずらす
営業時間を工夫するのも効果的な「ずらし」の一つです。
多くの店が開いていない時間に営業すれば、それだけで選ばれる理由になります。
例えば「朝5時から開店するカレー屋」や「深夜2時まで営業の和菓子カフェ」。
こうしたちょっと意外な時間帯の営業は、それだけで口コミになりやすいのです。
さらに「朝は健康志向のモーニング」「昼は定食」「夜はお酒とおつまみ」といった時間帯ごとの切り替えも効果的。同じ店舗でも、ターゲットやシーンを変えることで複数の需要を取り込めます。
実際に、昼はサラリーマンのランチでにぎわい、
夜はバーとして二毛作で成功しているお店も少なくありません。
ずらし系コンセプトを作る5ステップ
お店を始めるときに欠かせないもののひとつが「店名」です。どんなに料理や内装にこだわっても、名前が覚えにくかったり検索で出てこなかったりすると、お客さんに気づいてもらえない可能性があります。
逆に、シンプルで響きがよく、イメージが伝わる名前なら、口コミやSNSで自然と広まりやすく、集客にもつながります。
ここでは「ずらし系コンセプト」という少しひねった発想を取り入れながら、実際に店名を考えるための5つのステップを紹介します。
STEP1|キーワードをたくさん出す
まずは思いつくままに、できるだけ多くの単語を書き出してみましょう。
「カフェ」「ラーメン」「ビストロ」といった業態、「スパイス」「ナチュラル」「和風」といった特徴、自分の好きな言葉や思い出、地名、時間帯、数字、さらには「古い/新しい」「朝/夜」といった正反対の言葉まで、幅広く出すのがコツです。
最低でも30語くらい出してみると、後で組み合わせやすくなり、意外なアイデアも生まれやすくなります。
STEP2|似たもの同士をまとめて「タグ化」する
次に、出した言葉をグループ分けして整理します。
たとえば「朝・夜・深夜」は「時間タグ」、「森・川・空」は「自然タグ」、「古い・新しい・レトロ」は「時代タグ」といった具合にまとめてみましょう。
3〜5種類くらいのタグに整理すると、自分がどんな方向性で店を打ち出したいのかがはっきりしてきます。
「時間をテーマにするのか」「自然を前面に出すのか」「地域性を活かすのか」など、軸が見えてきます。
STEP3|ちょっと意外な「ずらし」を入れる
ここからが「ずらし系」の出番です。タグごとに整理した言葉に、半歩だけ意外性を加えてみましょう。
例えば…
- 「夜カフェ」ではなく「朝カフェ」と逆の時間を打ち出す
- 地域名と別の土地のイメージを組み合わせる(例:湘南+京都)
- 数字を加えてリズム感を出す(例:カフェ365、バー9)
- 言葉を英語やフランス語に置き換えて雰囲気を変える
ほんの少し視点を変えるだけで、「あれ、ちょっと気になるな」と思わせる名前になります。これが他店との差別化につながります。
STEP4|「語感テスト」
候補がいくつかできたら、必ず声に出してみましょう。10回くらい繰り返し言ってみて、スムーズに言えなければ不採用にするのがおすすめです。
また、友人や家族に5秒だけ見せて覚えられるかどうかもチェック。自然な略称にできるかも重要です。
難しい漢字や長すぎる名前は、看板で読みづらいだけでなく、電話予約や口コミで間違えられることが増えます。
「短くて言いやすい」「見てすぐわかる」名前だけを残していきましょう。
STEP5|最後は「検索」で確認
最後に必ずやっておきたいのが、権利関係も含め、ネット上での使いやすさの確認です。
- 商標検索:特許庁の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で同じ名前や似た名前が商標登録されていないか確認。
- ドメイン確認:「.com」「.jp」など、ホームページに使えるドメインが空いているかチェック。
- SNSアカウント確認:InstagramやX(旧Twitter)、TikTokで店名がすでに使われていないか調べる。
ここを疎かにすると、後から名前を変えざるを得なくなり、看板やメニューを作り直す費用が発生します。数十万円単位の損失になることもあるので要注意です。
ずらし系コンセプトをお店に活かすコツ
ユニークなアイデアや「ずらし系」の発想を形にするだけでは、お店を長く続けていくのは難しいものです。大切なのは、そのアイデアをちゃんと利益につながるように、集客の導線を考えていくことです。
集客を早く伸ばす
ここで便利なのが GoogleビジネスプロフィールとUberEatsのようなフードデリバリーサービスへの登録です。
たとえば昼と夜で雰囲気が違うお店なら、それぞれの写真を載せておくと印象が伝わりやすいです。また、道が分かりにくい場所にあるなら、スマホで見られる短い案内動画を用意すると安心して来てもらえます。
さらに、お客さんが自然と宣伝してくれる仕組みを作ることも効果的です。写真を撮りたくなるコーナーを作ったり、「#店名カフェ」といったハッシュタグを用意したりすれば、来店した人がSNSで発信してくれるようになります。
こうした「お客さんがつくる発信(UGC)」は、広告よりも信頼されやすく、口コミのように広がっていくのが魅力です。
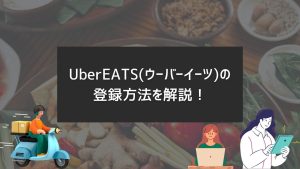
ずらし系コンセプトを作る際のチェックリスト
以下、ずらし系コンセプトを作る際のチェックリストです。
- アイデアを1文で説明できるか?
→ 複雑すぎる場合はコンセプトがまだ固まっていないサイン - ターゲットを絞れているか?
→ 誰でも歓迎は逆効果。特定の層に響く方が強い - 店名は短く、3〜6音に収まっているか?
→ 自然な略称ができるかもテスト - 商標・ドメイン・SNSアカウントの空き状況を確認したか?
→ 権利やネット上の発見性は後から直せない - 来店後に自然と発信したくなる仕掛けがあるか?
→ 写真映えスポット、ハッシュタグ、ストーリー性など - 時間帯ごとに収益モデルとオペレーションが無理なく回るか?
→ 席数・単価・回転数を基準にシミュレーション
よくある質問(FAQ)
- 造語はSEOに弱いですか?
-
単独の造語は検索に引っかかりにくいですが、工夫次第でカバーできます。おすすめは エリア+ジャンル+造語 の三語構成。たとえば渋谷 カフェ ノボリトなら、検索では渋谷 カフェで拾われつつ、造語部分で独自性を出せます。
- 店名はローマ字とカタカナ、どちらが良いですか?
-
国内向けなら カタカナのほうが読みやすく覚えやすい 傾向があります。ただし訪日客を意識するなら、看板やサイトにローマ字を併記しておくと安心です。両方をバランスよく使うことで、国内外のお客さんに対応できます。
- ニッチすぎるとお客さんが来なくならないですか?
-
市場が小さいと思う前に、まずは試算をしてみましょう。市場規模は エリア×時間帯×単価 で考えると整理しやすいです。最低限の売上ラインを計算し、その条件を満たせるなら十分成立します。むしろ絞り込むことで行きたい理由が明確になり、強い集客力を発揮するケースが多いのです。
まとめ
飲食店が選ばれる理由は味や内装だけではなく、ちょっと気になると思わせる工夫にあります。その方法がずらし系コンセプトです。
ターゲットを絞る、時間帯を工夫する、シチュエーションを限定するなど、半歩だけ視点を変えることで他店との差別化が可能になります。
さらに、店名は短く覚えやすいものが効果的で、口コミやSNSで自然に広がります。アイデアを成功させるには、利益を出せる仕組みに落とし込み、運営と集客を両立させることが大切です。
ずらし系を取り入れることで、お店は埋もれず、長く愛される繁盛店へと成長できるのです。